2025年3月12日に放送された『THE世代感 2時間SP』では、昭和時代のお菓子CMが紹介され、若い世代が驚いたポイントや、現代では問題視される可能性のある表現が議論されました。昭和の広告は時代背景を強く反映しており、現代の価値観から見ると「NG」とされる表現が含まれていることが明らかになりました。
昭和CMに見られる「性別役割の固定化」
代表的な例として挙げられるのが、1975年に放送された「ハウスシャンメンしょうゆ味」のCMです。このCMでは、「私作る人、ボク食べる人」というフレーズが使用されていました。この表現は、女性が料理を担当し、男性が食べるという性別役割を固定化するものとして批判を受け、放送中止に至りました。
時代背景と視聴者の反応
当時は男女平等の意識が徐々に高まりつつあった時期であり、このCMに対して女性団体から強い抗議が寄せられました。しかし、一般視聴者の間では「そこまで問題視する必要はない」という意見も多く、社会全体での意識の差が浮き彫りになりました。
現代基準で見た「差別的表現」
昭和時代には他にも、「貧乏百姓」や「かたわ」といった言葉が広告やドラマで使われていました。これらは現在では差別的とされるため、放送基準に基づき使用が禁止されています。また、性別や年齢による固定観念を助長するような表現も厳しく規制されています。
若い世代の驚きと学び
令和世代の視聴者は、昭和CMを見て「なぜこんな表現が許されていたのか」と驚きを隠せませんでした。一方で、当時の文化や価値観を学ぶ機会として受け止める声もありました。番組内では「広告は時代を映す鏡」というテーマで議論が展開されました。
昭和CMから学ぶべき教訓
昭和時代の広告表現は、その時代特有の価値観や社会構造を反映しています。現代では多様性や公平性を重視する社会へと変化しているため、過去の表現を批判するだけでなく、その背景を理解し教訓として活かすことが重要です。
この特集は視聴者に昭和と令和の価値観の違いを考えさせるきっかけとなり、大きな反響を呼びました。広告業界においても過去から学び、未来へ向けたより良い表現を模索する姿勢が求められています。

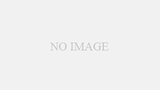
コメント